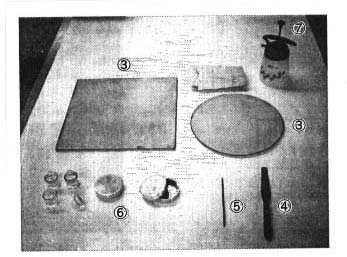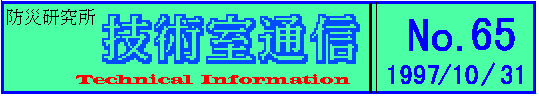
目 次
技術室職員研修会(第7回)を終えて …………………………………………… 1
液性限界・塑性限界試験(土の物理的性質の試験) …………………………… 2
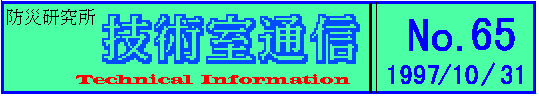
技術室職員研修会(第7回)を終えて …………………………………………… 1
液性限界・塑性限界試験(土の物理的性質の試験) …………………………… 2
技術室 小泉誠
穏やかな晴天にめぐまれ10月29・30日の2日間、理学部白浜臨海実験所の会場をお借りして防災研技術室職員研修会を行い無事終了しました。今回も昨年に続き借り上げバスを利用し、片道約5時間をかけた研修旅行となりました。1日目には災害観測実験センターの潮岬および白浜の教官による講義2題と技術職員による技術発表2件を行いました。2日目は技術討論会の終了後、臨海実験所の水族館および海象観測所の見学を行いました。水族館の見学では臨海実験所の3名の所員の方に説明を頂き一層理解を深めました。
今本防災研所長と技術室顧問の住友教授にはご多忙のなか両日共ご参加頂き、特に2日目の技術討論会には有益なアドバイスと激励を頂きました。企画側の準備不足でご迷惑をおかけした点が多々あったと思いますが反省点として今後に生かしたいと思います。
最後になりましたがこの技術室職員研修会は、所長はじめ研究所の諸先生方、事務部の方々のご理解とご協力により実現出来たものと感謝しています。とりわけ災害観測実験センター白浜海象観測所には企画当初から終始お世話になりました。また臨海実験所には快くお世話頂きました。記してお礼申し上げます。
はじめにこの試験は,土のコンシステンシー限界のうち,液性限界,塑性限界,および塑性指数を求めるために行う.これらはそれぞれ次のように定義されている.
液性限界:土が液体から塑性体に移る境界の含水比をいう.試験方法では,試料を入れた皿を1cmの高さから1秒間に2回の割合で25回自由落下させたとき,二分した溝の両側から土が流れ出して長さ約 1.5 cm 合流するときの含水比と規定している.
塑性限界:土が塑性体から半個体に移る境界の含水比をいう.試験方法では,土を転がしながらひも状にして直径3mmになったとき,ちょうど切れぎれになったときの含水比と規定している.
塑性指数:液性限界と塑性限界の差をいう.
さて,私が関係する仕事上の土質試験の一部分をここに紹介いたします.
練混ぜた粘性土は,その含水量によって液状,塑性状,固体状といろいろ変化する.
これは土粒子のくっつき方,すなわち外力を受けた時の流動,変形に抵抗する度合いが変わるためで,この性質を土のコンステンシーという.
この変化が進行する段階の含水量は土の種類によって異なるので,これを測定して粘性土の性質を知り,これを判別分類の基準として利用することが広く行われるようになった.このコンステンシーの限界として,現在試験法に定められているのは液性限界,塑性限界,収縮限界の3種類があり,そのうちの液性限界と塑性限界試験を行っています.
また,液性限界試験を行う際,試料に蒸留水を少しずつ加えてする方法と,逆に自然乾燥により脱水して行う方法があるが,私の経験からでは前者の方は早く出るが,結果にムラが多く,後者の方法で行う方がいいようである.そして塑性限界試験は試料をすりガラス板上に手のひらで,軽くころがすようにしてやるのだが,3mm位のひも状にするまでに切れぎれになってしまうことが多く,けっこう手間どってしまう.又,人によって値も差が出やすい.
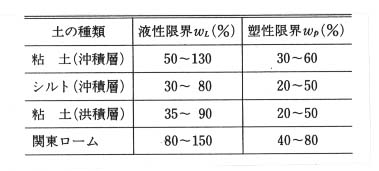
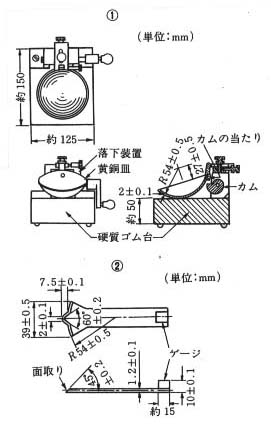
試験用具の例