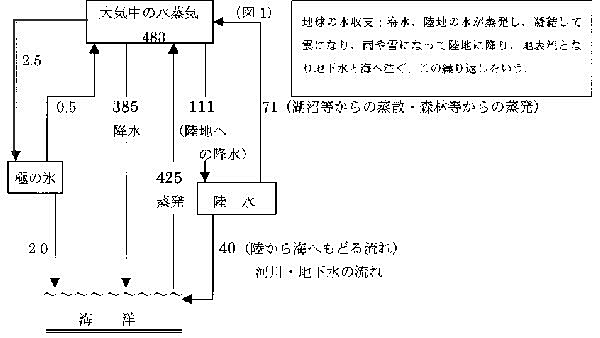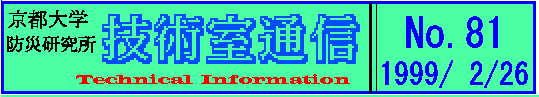
目 次
和歌山での技術支援事始め ―――――――――――― 1
釣り雑文 ―――――――――――――――――――― 2
水は誰のものか ――――――――――――――――― 6
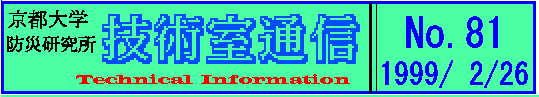
和歌山での技術支援事始め ―――――――――――― 1
釣り雑文 ―――――――――――――――――――― 2
水は誰のものか ――――――――――――――――― 6
| 貯留量(km3) | 割合(%) | 循環の速さ(km3/年) | 平均滞留時間 | |
| 海 洋 | 1,349,929,000 | 97.5 | 418,000 | 3,200年 |
| 氷 雪 | 24,230,000 | 1.75 | 2,500 | 9,600年 |
| 地下水 | 10,100,000 | 0.73 | 12,000 | 830年 |
| 土壌水 | 25,000 | 0.0018 | 76,000 | 0.3年 |
| 湖沼水 | 219,000 | 0.016 | 数年~数十年 | |
| 河川水 | 1,200 | 35,000 | 13日 | |
| 水蒸気 | 13,000 | 483,000 | 10日 | |
| 総 計 | 1,384,517,000 | 100 |